安っぽいテレビ番組から「究極の選択」という質問を受けたことがある。
「最後の人類として土壌が豊かではない孤島に暮らす」として
以下のどちらかを選べるとしたら、というものだった。
A「健康美人系グラビアガール」
B「かなり年増の女性と食料1年分」
質問の意図は、極限状態で性欲と食欲のどちらが優先されるのか。
Aと答えた。繁殖できなければ、食料がいくらあっても意味がない。
テレビのスタッフが「食料10年分なら?」と選択肢Bの価値を上げた。
食料10年分という発想が、都市文明に脳が芯まで侵されていることを示している。
食べ物とは共に生きる生物すべてである。
近い将来に食べるものが、いまもどこかで生きている。
いまもどこかで継がれつづける命が、遠い未来の食べ物になる。
食べるとは多くの命と共に生きていくことに他ならない。
生きるとは、多くの生き物が溢れる環境の中で、
自分もただひとつの生命体として正しく振る舞うことである。
それは獲物を獲ることであり
もしくは逆に、自分が獲物になることでもある。
文/服部文祥
写真家 石川竜一
1984年沖縄生まれの沖縄顔。2014年に写真集『絶景のポリフォニー』『okinawan portraits 2010-2012』を同時刊行して鮮烈なデビューを飾り、その年の木村伊兵衛写真賞を受賞。現在、国内外でもっとも注目されている新進気鋭の写真家。
登山家 服部文祥
1969年横浜生まれの沖縄顔。オールラウンドな登山から、食料を現地調達するサバイバル登山を始め、『ツンドラ・サバイバル』で梅棹忠夫山と探検文学賞を受賞。100年以上の歴史がある文芸誌に狩猟者的思想の創作を発表する登山家。
新鋭写真家とともに
石川竜一といえば、その世界では知らない人がいない若手の注目株らしい。その世界とは写真業界、アート業界といったところである。新聞や文芸誌などインテリジェンスな世界でも評価が高いようだ。つい先日までおこなわれていた横浜美術館の企画展にも芸術家たちに混じって、ただ一人写真家として作品を発表していた。
2015年の初めに、石川県の金沢で写真集を中心に出版活動をしているSLANTの日村さんから連絡を受けたのが、石川竜一との交流の始まりだった。
「面白い若手写真家がいるので、いっしょに山に行ってくれませんか」と日村さんが言った。ちなみに日村さんと話すのもそれが初めて。注目の写真家に、サバイバル登山を体験させたら、なにを撮るのか興味があるらしい。それなりの作品が集まったら写真集にするという目論見で、本人も同意しているという。
フォトグラファーと山に行くことは多い。全登山の八割くらいはカメラマンといっしょである。そのカメラマンたちも山の情景を切り取る技は長けている。だが「アート系写真家」といっしょに山に行ったことはない。サバイバル登山を写真作品にするというのはちょっと興味を惹かれた。おおかたのエリアは登り尽くし、サバイバル登山に新鮮さが減りつつあると感じていた私にとっても、新しい体験になるかもしれない。
「いくらでいっしょに行ってもらえますか」と日村さん。
「ガイドはやってません」と私は答えた。「そもそも、連れて行ってもらっても山とはなにかなんかわからないですよ。山に登りたいという意志があるなら、山仲間としていっしょにいきましょう」
というわけで、そのプロジェクトは発動することになった。気軽に請け負ったものの、ちょっと不安になり、石川竜一の人となりと作品を私は調べた。高校時代にボクシングで国体3位という実績があるらしく、体力と空腹対応には問題がなさそうだった。作品はちょっと挑発的なアート系という感じ。プロアマ問わず写真を撮っている人に「石川竜一って知ってる?」と聞いてみたが、誰も「誰それ?」とは言わない。反応はほぼふたつ。ひとつは「ああ、あれね」というちょっと蔑んだ鼻息。もうひとつは「え?なんで服部の口からあの石川竜一さまの名前が出てくるの」という驚き。なんと後者のほうが圧倒的に多く、評価が結構高いらしい。
だが私がその作品を見て最初に思ったのは、だれがこんなものを見て喜ぶのだろうという素朴な疑問だった。雑誌作りの現場に20年もいるからかもしれないが、私には石川竜一の写真に実用性が感じられなかった。

写真と表現
写真にかぎらず「表現活動の実用性」というのは、芸術もしくは文化人にとって大命題である。絵も文字も写真もそもそもは記録したり、何かを伝達したりするために生まれたものだ(たぶん)。たとえばこのページで使われているえぐい写真は、編集長の川崎が撮ったものだが、鹿猟の現場を伝えて、ひと目を引くという雑誌作りとしての実用性がある。「バカやってらぁ」とか「すごい情景ですね」などと誰かが雑誌を購入し、経済活動を促す有用性である。ひいてはそれが川崎の給料となり、川崎とその家族が生きていくことにつながっている。
ようするに「実用性」は「お金を回すため(生活のため)」にたどり着く。ところが、私は芯のところでお金というものを信用していない。「猫に小判」という通り、お金は人間社会の中だけで通用する約束事に過ぎないからだ。
石川竜一と行った最初の人間社会の外側は、加賀白山山系でのプチ・サバイバル登山だった。そこに石川竜一がもってきたハッセルブラッド(バカでかいカメラ)は、半日で動かなくなった。そもそも湿気に弱いうえに、中古で調子も悪かったらしい。しかたなく、私のサイバーショットを貸して、撮影サバイバル山行を続けた。
世界的に注目されているらしい写真家は、小さなコンデジを手に、ゴソゴソしてばかりで、歩かない。ようすを見るとメモリーがいっぱいになったと、いらない写真を探して消していた。最大画素で400枚くらい撮れる容量があったはずだが、一日で全部いっぱいにしてしまったらしい。
「メモリーに残っている俺の写真は全部消していいよ」というと、子供のような弾けんばかりの笑顔が返ってきた。
山旅の終盤、渓を登りきって稜線に出た。尾根上に池塘があり、なんとそこで、産卵に来たモリアオガエル(希少種)が何匹も小動物に食い荒らされていた。しかもどのカエルも食べられているのはモモ肉だけ。天然記念物とか絶滅危惧種とかいう人間の評価は自然界の食料事情にはなんの効力もない。当たり前のことだが、それがモモ肉だけを食い散らかされたモリアオガエルになって具現化されているのが、私には面白かった。
「これ撮りなよ」と石川竜一にいうと、面倒くさそうにして動かなかった。写真に関して指図されるのがあまり好きではない上に、どうやら登山で相当疲れているらしい。
座り込んだままの石川竜一から「ちょっと貸して」とカメラを受け取って、目の前の風景を写真に収めながら、私はその光景に隠された意味を話した。
少し感心したように聞いていた石川竜一は、写真を撮り終えた私からサイバーショットを受け取ると、それじゃちょっと、という感じでモリアオガエルを撮りはじめた。
一通り撮り終えた頃に、「見せて」とカメラのモニターを確認して私は息を飲んだ。同じ物を同じカメラで同じように撮ったはずなのに、作品としての迫力が違ったのだ。サイバーショットの小さなモニターでもそれははっきりわかった。
こいつ写真上手なんだな、と山旅を4日ともにしてようやくわかった。
表現に実用性を求めてそれを突き詰めると、その根本は、人間の約束事に帰結する。実用性という評価のしかたに問題が隠れているのだ。
そもそも私自身が文字表現や登山表現に実用性を求めていない。表現とは、なにかを伝えるための手段ではなく、純粋な目的である。「写真」という媒体の性格に引っ張られて濁っていたのは、私の目のほうだった。石川竜一が人間の約束事を越えた写真を求めているとしたら、「実用性が感じられない」という私の評価は、明後日の方向を見た的外れなものということになる。写真が手段ではなく目的なら、たとえば重いハッセルブラッドを山に持ってくる非効率が、最大効率にだってなる(故障は別)。
2015年9月にもう一度、二人で一週間ほどのサバイバル登山に出かけ、ふたつの登山が『CAMP』という写真集となった。モリアオガエルの写真はその『CAMP』と『フィールダー別冊・獲物山』におさめられている。

そして冬が目的になる
山の中で雨や雪に降りこめられ、やることがまったくない時間に、ボソボソと石川竜一と話すことがある。「表現とその実用性」に関しては、こま切れにだが、多少深い部分まで意見を交換した。人類の文明が作り出したカメラという機械で、その文明が包括できないなにかを写し撮ろうとしているなら、人間の約束事の内側に暮らしながら、ときどきその檻の外で遊ぼうとする私と、見ている方向は同じかもしれない。
夏のサバイバルが成功したからというわけではなく、たぶん純粋な目的として、最近、石川竜一といっしょに猟に出かけている。
「そんな写真を何頭分撮れば作品としてまとまるんだ?」と私は問う。
「100頭分くらいですかね」と怖いことを言って笑う。
石川竜一は獲物を食べるのも大好きである。沖縄でヤギ汁に慣れているから、鹿も臭ければ臭いほど好みらしい。

Fielder別冊
獲物山
服部文祥のサバイバルガイド
1600円(税別)
服部が獲物にまつわる山旅と思想を写真と文章で報告する。この出猟で撮られた石川竜一作品も、かなり強烈なグラビアページとなっているので、発禁処分になる前にまずはご覧いただきたい(立ち読みでもいいので)。




















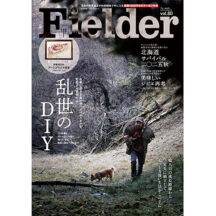










2人で歩いた出猟日記
2016年11月下旬と12月上旬、獲物を求めて2人で山を歩く。服部はブローニングで獲る。石川はハッセルブラッドで撮る。殺しは手段であり目的でもある。行為者の中でバランスは取れている。
この2人、どこの馬鹿ヤンキーですか?