今年の八丈島の梅雨は雨量が多く、家に閉じ込められる日々が続いた。島全体が白い靄に包まれ、湿度は100%。家の中はどこもかしこもカビが発生しまくって堪らない。軽トラのサイドブレーキも潮と湿気で錆びて、ボキッと折れて坂道には止められない車になってしまった。
磯からの土砂崩れの影響で海も白く濁りがちだけど、梅雨の晴れ間に海に繰り出すと、夏の風物詩である産卵期のカンパチが徐々に姿を現してきた。他の魚と違いカンパチはケタ違いに好奇心が強い。当然個体差があるけれど、泳いでいる人間を見つけると「えっ?何やっているの?」とこちらに近寄ってくる。そこを銛で一突き。少し申し訳なくなってしまうほど簡単に結構な大きさのカンパチが食べられる。
この時期のぼくとその周りの人たちの肉体はカンパチとビール、もしくは焼酎でほぼ構成されていると思う。世間的に高級とされているカンパチは人にあげても喜ばれるし、なかなか良いとこ尽くしの魚だ。とはいえ、シーズン初めは嬉しかったカンパチも、贅沢だけれどだんだんと食傷気味になってくる。海で泳ぎながら、食べ切りサイズの子豚のような四つ足動物が泳いでいないかな、とつい妄想してしまう。
そんな生活を送っているからか、島の中心街のスーパーでお年寄りが内地からわざわざ送られてきた九州あたりの養殖カンパチを買って帰る姿を見ると、海に囲まれて生活しているのにと寂しい気持ちになってしまう。悲しいことに価格競争がない島産の魚よりも内地から取り寄せた魚の方が安い。だから我家では基本的に魚類は自分で獲ってくる以外は買わないし、魚がいっぱい獲れた時はなるべく近所の人たちに配ることにしている。
福島から毎夏やってくる少年は八丈の海で魚突きの味を覚えてしまい、家に帰ってから「将来は八丈に住んで漁師になる」と泣いて言い張って親の度肝を抜いたと聞いた。ほくそ笑むと同時に、同じ中毒症状を持つ身としては新しい世界を知ってしまった少年の気持ちが痛いほどよくわかる。そして、彼の故郷・福島の海がいまなお汚染され続けていることを考えると余計に切ない。
子供の頃、シベリアに抑留されていた祖父に「戦争で人を殺したことあるの?おじいちゃんはなんで戦争に反対しなかった?」と尋ねて「みんなそうだったんだから、仕方がなかったんだよ」と自分に言い聞かせるよう寂しそうに答えた祖父と同じように、もし僕がこの少年に「なんで危険な原発が今もあるの?」と無邪気に尋ねられたらきちんと答えられないと思う。
あたかも東京だけが世界の中心のようにオリンピック開催に浮かれてお祭り騒ぎへと突き進んで行く中、沖縄や福島の問題は地方の問題として切り離されていく。政治やメディアは社会全体の憎悪や恐怖を煽り、共通の敵を作り出し、それが他者への想像の欠如になって緩やかなファシズムと同心円状につながっていっているのだと思う。そして集団は個を押し潰して不確かな情報や刺激に過敏に反応し、暴走する。スマートフォンをタップするだけで血も汗も流さずに、極端にいえば他者とも交わらずに生きていける世の中は究極の時代を迎えつつあるのかもしれない。
生活の中で「生」の手触りを感じることができなくなればなるほど「死」に付随する痛みや喪失に対しても希薄になっていくのだと思う。生命の根幹の大事なものさえ守ることができない社会は、死に向かって徐々に体が病に蝕まれていくかのようだ。
最近の香港やベネズエラで、自分たちの社会の土台=自由を命がけで守ろうとする彼らの姿を目にする度に、傍観しているこちら側へ「お前達はどうするんだ」と問われている気がする。
亀山 亮
かめやまりょう◎1976年生まれ。パレスチナの写真で2003年さがみはら写真新人賞、コニカフォトプレミオ特別賞。著書に『Palestine:Intifada』『Re:WAR』『Documen tary写真』『アフリカ 忘れ去られた戦争』などがある。13年『AFRIKA WAR JOURNAL』で第32回土門拳賞を受賞。新作写真集『山熊田 YAMAKUMATA』を2018年2月に刊行。









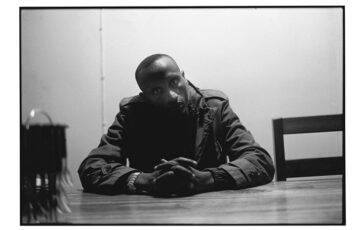





















メキシコ・ゲレロ州/自分で捕まえた鹿の頭の骨を持つ老人。